アニサキスとは
 アニサキスは、サンマ・サバ・アジ・サケ・カツオ・タイ・イカなどの魚介類に寄生する寄生虫です。生きている魚の内臓に棲みついていますが、魚が死ぬと筋肉部分へと移動する性質があり、その部分を食べた人の体内に入ることがあります。
アニサキスは、サンマ・サバ・アジ・サケ・カツオ・タイ・イカなどの魚介類に寄生する寄生虫です。生きている魚の内臓に棲みついていますが、魚が死ぬと筋肉部分へと移動する性質があり、その部分を食べた人の体内に入ることがあります。
この寄生虫は、白く細い糸のような形状で、長さは約2cmと肉眼でも確認できる大きさです。
アニサキスは加熱または冷凍処理によって死滅しますが、処理が不十分な場合には感染のリスクが残ります。正しい処理を施せば、感染の可能性は大きく減少します。
なお、アニサキスは人間の体内で成長・繁殖することはできず、通常は数日から1週間程度で自然に死滅します。
症状
胃アニサキス症の場合
主な症状は、突然起こる強い胃の痛みです。一時的に痛みが治まっても、再び痛みがぶり返すことがあり、吐き気や嘔吐を伴うケースも見られます。
アニサキスが寄生した魚介類を食べてから数時間から十数時間以内に症状が現れることが多く、アニサキスが胃粘膜に身体を刺し込むことで激しい痛みを引き起こします。この痛みは、アレルギー反応によるものと考えられています。
診断と治療には胃カメラ検査が有効で、検査中にアニサキスの虫体を発見すれば、その場で摘除することが可能です。虫体が見つからなくても、胃粘膜の発赤やむくみ、びらんなどが認められた場合には、胃アニサキス症と診断されることがあります。
腸アニサキス症の場合
突然の激しい下腹部痛が特徴です。場合によっては、腹膜炎に似た症状として、嘔吐・発熱・頻脈などを伴うこともあります。
アニサキスが小腸に入り込むことで発症しますが、小腸は胃カメラでは観察できないため、診断にはCT検査や問診が必要となります。 アニサキスを含む魚介類を摂取してから、十数時間から数日後に症状が現れるため、「原因に心当たりがない」と訴える方も多いです。
ごく稀ではありますが、腸閉塞や腸穿孔といった深刻な合併症を引き起こす可能性もあるため、強い腹痛が続く場合は早めの受診が重要です。
消化管外アニサキス症の場合
アニサキスが消化管の粘膜を通り抜けて腹腔内に侵入すると、肉芽腫というしこりのような病変を形成することがあります。
肉芽腫が生じた部位によって症状には違いがあります。
アニサキスアレルギーの場合
既に死んでいるアニサキスや完全に除去されたものであっても、体がアレルゲンとして反応してしまう状態です。加熱や冷凍処理を十分に施しても、アレルギー体質の方が摂取すると症状が現れることがあります。
特に、サバなどの青魚を食べた後に蕁麻疹などのアレルギー症状が出た場合は、アニサキスアレルギーが疑われます。 重症例では、呼吸困難などを引き起こすアナフィラキシーショックに至ることもあります。
治療
胃アニサキス症の場合
胃アニサキス症では、胃カメラ検査により寄生しているアニサキスを直接摘除します。多くの場合、摘除後すぐに痛みが和らぎますが、体がアニサキスに対してアレルギー反応を起こしている場合には、摘除後もしばらく痛みが続くことがあります。
この場合、抗アレルギー薬や抗ヒスタミン薬、ステロイド、鎮痛薬などを併用しながら症状の緩和を図ります。
腸アニサキス症の場合
小腸に寄生しているアニサキスは胃カメラでは除去できないため、絶食や点滴などによる対症療法が中心となります。
ごく稀に、腸閉塞や腸穿孔などの重篤な合併症を起こすことがあり、その場合には外科的処置が必要となることもあります。
予防
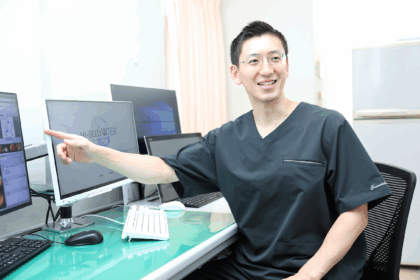 アニサキスは、加熱や冷凍処理によって死滅するため、魚を安全に食べるにはしっかりと火を通すか、マイナス20℃以下で24時間以上冷凍保存することが効果的です。特に生魚を食べる場合は、冷凍処理された刺身を選ぶようにしましょう。
アニサキスは、加熱や冷凍処理によって死滅するため、魚を安全に食べるにはしっかりと火を通すか、マイナス20℃以下で24時間以上冷凍保存することが効果的です。特に生魚を食べる場合は、冷凍処理された刺身を選ぶようにしましょう。
また、アニサキスは肉眼で確認できる大きさで、ブラックライトを照らすとよりはっきり見えることから、専門の業者が適切に処理した魚を選ぶことで、感染リスクは大きく下げられます。ただし、アニサキスアレルギーがある方は注意が必要です。
既に死んでいるアニサキスや、完全に取り除かれた状態であっても、アレルギー反応を引き起こす可能性があるため、寄生のリスクがある魚介類の摂取は控えましょう。







