バレット食道とは
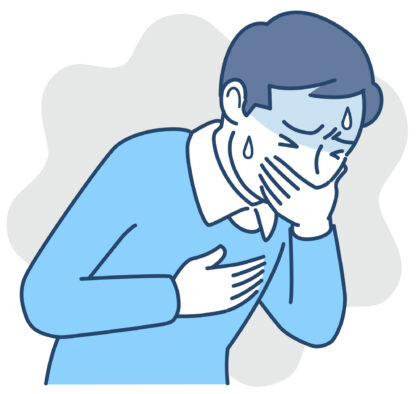 バレット食道とは、主に逆流性食道炎の進行によって生じる病態です。通常、食道の内側は扁平上皮という細胞で覆われていますが、胃酸の逆流によって炎症が繰り返されることで、この扁平上皮が胃や腸に見られる円柱上皮へと置き換わってしまう状態を指します。
バレット食道とは、主に逆流性食道炎の進行によって生じる病態です。通常、食道の内側は扁平上皮という細胞で覆われていますが、胃酸の逆流によって炎症が繰り返されることで、この扁平上皮が胃や腸に見られる円柱上皮へと置き換わってしまう状態を指します。
この置き換わりの範囲によって、バレット食道の重症度や食道がんへのリスクが判断されます。粘膜の変化が噴門(胃と食道の境目)から3cm未満であれば「SSBE(Short Segment Barrett's Esophagus)」と呼ばれ、がん化のリスクは比較的低いとされています。
一方、3cm以上に及ぶ場合は「LSBE(Long Segment Barrett's Esophagus)」と呼ばれ、食道がんの発症リスクが高まる状態と考えられています。実際、LSBEでは年間約1.2%の割合でがん化が報告されています。
食道がんの患者数は近年増加傾向にあり、その要因の1つとしてバレット食道が注目されています。
バレット食道の原因
バレット食道の主な原因は、胃酸が食道へ逆流することで生じる慢性的な刺激です。食道粘膜は胃酸に対する耐性が低く、繰り返し胃液に晒されることで炎症が起こり、逆流性食道炎を引き起こします。
この炎症が改善と再発を繰り返すうちに、食道の本来の粘膜である扁平上皮が、胃や腸に見られる円柱上皮へと置き換わってしまい、バレット食道へと進行します。
近年では食生活の欧米化などにより、逆流性食道炎の患者数が増えています。放置してしまうと、バレット食道を経て食道がんに繋がる恐れがあるため、早期の対応と継続的な管理が重要です。
バレット食道の主な症状
 バレット食道は逆流性食道炎を背景に発症するため、逆流性食道炎と同じ症状が現れます。
バレット食道は逆流性食道炎を背景に発症するため、逆流性食道炎と同じ症状が現れます。
主な症状は以下のとおりです。
- 胸やけ
- げっぷや呑酸(酸っぱい液が口まで上がってくる)
- のどの違和感や異物感
- 飲み込みにくさ(嚥下困難)
- 風邪をひいていないのに咳が続く
- お腹の張り
- 吐き気 など
ただし、胃酸の逆流があっても自覚症状がほとんど現れない方もいます。
バレット食道の検査・診断
 バレット食道は逆流性食道炎が長期的に続くことで発症するため、まずは問診にて、現在の症状、過去の病歴、生活習慣などを詳しくお伺いします。
バレット食道は逆流性食道炎が長期的に続くことで発症するため、まずは問診にて、現在の症状、過去の病歴、生活習慣などを詳しくお伺いします。
逆流性食道炎の可能性がある場合、胃カメラ検査を実施し、食道や胃の入り口付近の粘膜の状態を直接確認します。検査中に異常が認められた場合は、粘膜の一部を採取して病理検査を行い、バレット食道かどうかを確定診断します。
バレット食道と診断された場合には、がん化リスクの評価と早期発見のために、定期的な胃カメラ検査による経過観察が重要となります。
バレット食道の治療
現在の医療では、一度置き換わった円柱上皮を扁平上皮に戻す治療法は存在しません。そのため、逆流性食道炎を適切に治療し、進行を防ぐことが中心となります。
胃酸の逆流を抑える薬物療法に加え、暴飲暴食、脂っこいものや刺激物の摂取は控えましょう。禁煙・節酒、肥満の改善、腹圧がかかる姿勢の回避といった生活習慣の見直しも大切です。
バレット食道のよくあるご質問
バレット食道と診断されました。食事で注意すべきことはありますか?
バレット食道は、胃酸の逆流によって食道の粘膜に炎症が繰り返されることで起こります。そのため、食事においては暴飲暴食を避け、脂っこい料理や刺激の強い食べ物を控えることが大切です。加えて、早食いや食後すぐに横になるといった習慣も胃酸の逆流を促すため注意が必要です。
バレット食道と診断されましたが、食道がんのリスクが高いですか?
日本人に多いのは、噴門から3cm以内の範囲で円柱上皮に置き換わっているSSBEというタイプで、この場合は食道がんになるリスクは比較的低いとされています。
一方で、円柱上皮化が噴門から3cm以上に及ぶLSBEの場合は、がん化の可能性が年間約1.2%と報告されており、ややリスクが高い状態となります。
SSBEと診断されましたが、治療を受けるべきですか?
現在の医療では円柱上皮に置き換わった粘膜を下の状態に戻す治療法が存在しません。なお、逆流性食道炎を放置すると円柱上皮化が進行する可能性があるため、胃酸の逆流を抑える治療を継続し、併せて食生活や生活習慣の見直しを行うことが重要です。







