脂肪肝とは
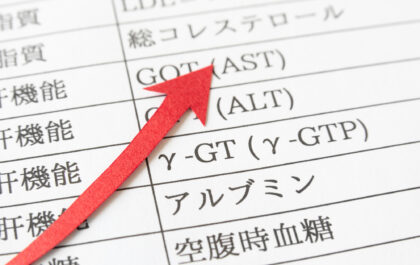 脂肪肝とは、肝臓細胞の30%以上に中性脂肪がしずく状に蓄積された状態を指します。主に運動不足や食べ過ぎ、アルコールの過剰摂取などの生活習慣が背景にあり、年々増加傾向にあります。肝臓の疾患の中でも最も多く見られる病気とされ、日本では健康診断を受けた男性の約3割、女性の1割に脂肪肝が認められています。
脂肪肝とは、肝臓細胞の30%以上に中性脂肪がしずく状に蓄積された状態を指します。主に運動不足や食べ過ぎ、アルコールの過剰摂取などの生活習慣が背景にあり、年々増加傾向にあります。肝臓の疾患の中でも最も多く見られる病気とされ、日本では健康診断を受けた男性の約3割、女性の1割に脂肪肝が認められています。
脂肪肝は進行すると慢性肝炎や肝硬変に至る恐れがあり、さらに重度になると肝不全や肝臓がんの原因となることもあります。
ただし、早期に対処すれば、多くの場合は生活習慣の改善によって回復が見込めます。当院では、日頃の食生活や運動習慣などについて丁寧に伺いながら、それぞれの方に合わせた具体的なアドバイスを行っています。血液検査や腹部超音波検査などを活用しながら、段階的に状態を確認し、改善に向けてしっかりとサポートいたします。健康診断などで肝機能に異常が見つかった際は、できるだけ早くご相談ください。
原因
脂肪肝は、過剰な飲酒、肥満、糖尿病といった生活習慣に関連した要因によって発症することが多く、脂質異常症(高脂血症)が背景にある場合もあります。また、甲状腺機能亢進症や、ステロイドなどの薬剤の使用が引き金となっているケースも確認されています。
アルコールとの関係
日本酒に換算して1日平均5合以上(エタノール100g相当)の飲酒を5日以上続けると、80%を超える確率で脂肪肝を発症すると言われています。
肥満との関係
BMI25以上の方では、約30%に脂肪肝が見られ、BMIが30を超えると、その割合は80%にまで上昇します。
糖尿病との関係
糖尿病は脂肪肝の重要なリスク因子ですが、逆に脂肪肝の存在がインスリンの作用を妨げ、糖尿病の発症や進行に影響を及ぼすこともあります。
分類
脂肪肝は大きく分けて、アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の2つに分類されます。
判定の基準はエタノールの摂取量で、1日あたりの摂取量が30g以下であればNAFLDに分類されます。 NAFLDはさらに、肝臓に脂肪が溜まっているだけの「単純性脂肪肝」と、炎症や肝細胞の障害を伴う「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」の2つに分けられます。
特にNASHは、肝硬変や肝臓がんへ進行するリスクがあるため、早期の発見と継続的な経過観察が重要です。
症状
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)は、多くの場合で自覚症状がなく、健康診断などで肝機能異常を指摘されたことをきっかけに発見されるケースが大半です。
一方、アルコール性脂肪肝も初期段階では目立った症状が現れにくいものの、病状が進行するとアルコール性肝炎やアルコール性肝硬変へと移行することがあります。これにより、倦怠感や胸やけ、心窩部痛、吐き気、食欲不振、吐血などの消化器症状が現れるほか、手足の痺れや歩行障害、さらには抑うつ傾向や睡眠障害などの神経・精神症状を伴うこともあります。
重症化を防ぐためには、アルコールの摂取を中止することが非常に重要です。
治療
 アルコール性脂肪肝の治療には、禁酒が欠かせません。飲酒を止めることで、肝機能の異常や障害の改善が期待でき、アルコール性肝炎や肝硬変への進行を防ぐことが可能です。加えて、良質なタンパク質を摂取し、ビタミンやミネラルのバランスが取れた食生活を意識することも、治療の一環として効果的です。
アルコール性脂肪肝の治療には、禁酒が欠かせません。飲酒を止めることで、肝機能の異常や障害の改善が期待でき、アルコール性肝炎や肝硬変への進行を防ぐことが可能です。加えて、良質なタンパク質を摂取し、ビタミンやミネラルのバランスが取れた食生活を意識することも、治療の一環として効果的です。
一方、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の主な原因は過食にあるため、余分な脂質を控えるとともに、カロリーの適切な制限が必要です。具体的には、身長から算出した適正体重1kgあたり30kcalを1日の摂取目安とします。適正体重は、身長(m)×身長(m)×22で求められます。肥満がある場合は、現在の体重の7%を目標に減量を進めます。
中性脂肪を減らすためには、アルコールや脂質、糖質の摂取を控え、有酸素運動を日常的に取り入れることが重要です。また、糖尿病や脂質異常症などを併発している場合には、それらの病気の治療とコントロールも欠かせません。体重を適正に保つことは、合併症の改善にも繋がります。







