逆流性食道炎とは
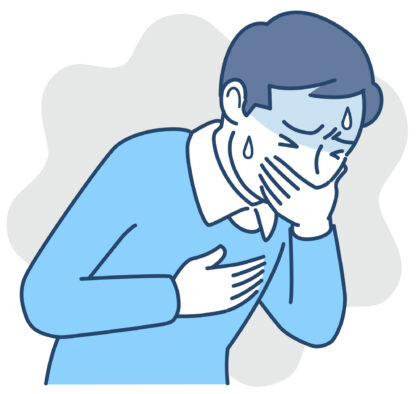 逆流性食道炎は、胃の内容物が食道へ逆流し、食道粘膜に炎症を引き起こす病気です。
逆流性食道炎は、胃の内容物が食道へ逆流し、食道粘膜に炎症を引き起こす病気です。
胃には強力な胃酸に対する防御機能がありますが、食道にはそれが備わっていないため、逆流した胃酸が炎症の原因となります。胃酸の逆流を防ぐ仕組みには筋肉の働きが深く関与しており、加齢により筋力が低下すると発症リスクが高まります。さらに、肥満や腹部の圧迫による腹圧の上昇、脂肪やタンパク質を多く含む消化に時間がかかる食事も原因となるため、幅広い年代で発症数が増えています。
胸やけなどの症状は、市販薬で一時的に緩和できることもありますが、再発しやすく、慢性化するケースも少なくありません。炎症が長期間続くと、食道がんのリスクが高まる可能性もあるため、症状が改善しない場合は医療機関で適切な治療を受け、再発予防に努めることが大切です。
逆流性食道炎の主な症状
- 呑酸(酸っぱいげっぷ)
- のどの違和感
- 飲み込みにくさ
- のどのつかえ感
- 胸やけ
- 胸痛
- 胃もたれ
- 心窩部痛
- 長引く咳
- 声がれ
など
逆流性食道炎の原因
食道裂孔の緩み
胸部と腹部の間には横隔膜があり、食道はその横隔膜にある「食道裂孔」という隙間を通って、胸部から腹部の胃へと繋がっています。この食道裂孔は、通常であれば筋肉によってしっかりと締め付けられていますが、加齢などで筋肉が弱くなると締まりが緩み、胃酸が食道へ逆流しやすくなります。
さらに、裂孔の緩みが大きくなると、胃の上部が胸部側へ飛び出す「食道裂孔ヘルニア」を引き起こすことがあり、逆流性食道炎のリスクがより高まります。
下部食道括約筋の衰え
下部食道括約筋は、食道と胃の接合部に位置し、通常は締め付けることで胃の内容物が食道へ逆流するのを防いでいます。
この筋肉も加齢により機能が低下すると、締め付ける力が弱まり、逆流リスクが高まります。
蠕動運動の低下
消化管は、蠕動運動により内容物を先へと送り出しています。逆流が起こった場合でも、蠕動運動がしっかり機能していれば、胃の中へと速やかに戻されます。
しかし、この蠕動運動の働きが低下すると、逆流した内容物が食道内に留まりやすくなり、粘膜に炎症を起こす原因となります。
腹圧の上昇
腹圧が高まると、胃への圧力も強くなり、胃の内容物が逆流しやすくなります。
腹圧上昇の主な要因としては、肥満や締め付けの強い衣類、猫背などの姿勢のほか、運動や重い物を持ち上げる動作などが挙げられます。
生活習慣の乱れ
食後すぐに横になると、胃の内容物が食道に逆流しやすくなります。
さらに、脂肪やタンパク質を多く含む食事は胃酸の分泌を促し、消化に時間がかかるため、逆流性食道炎のリスクを高める要因となります。
内服薬の副作用
喘息や心疾患、高血圧などの治療で使われるお薬の中には、副作用として筋肉を緩めてしまうものがあり、それが原因で逆流性食道炎を引き起こすことがあります。日常的にお薬を服用している方は、受診時にお薬手帳など、現在服用中のお薬が全て分かるものを持参してください。副作用が原因であれば、処方内容を変更することで逆流を防げる場合があります。お薬の変更が難しい場合でも、逆流性食道炎に対する適切な治療を行うことで、症状の軽減や食道粘膜の炎症を抑えられます。
なお、ピロリ菌の除菌治療後に胃の状態が元に戻り始めたタイミングで、一時的に逆流性食道炎のような症状が出ることがあります。このようなケースでは基本的に特別な治療は不要ですが、症状が強く出ている場合には、適切なお薬を使用することで症状の改善が見込めます。
検査
 逆流性食道炎の診断には、食道の粘膜を直接観察できる胃カメラ検査が有効です。
逆流性食道炎の診断には、食道の粘膜を直接観察できる胃カメラ検査が有効です。
検査中に組織を採取して病理検査を行うことで、確定診断を下せます。また、逆流性食道炎と類似した症状を引き起こす胃の疾患や、食道裂孔ヘルニアの有無についても併せて確認できます。さらに、炎症の広がりや重症度を詳しく把握できるため、適切な治療計画を立てるうえで非常に有用です。
当院では、経験豊富な医師が、最新の内視鏡機器を用いて細部まで丁寧に観察し、苦痛の少ない胃カメラ検査を心がけています。鎮静剤を使用することで、ほとんど眠っているような落ち着いた状態で検査を受けられるため、不安に感じている方も一度ご相談ください。
治療
胃酸分泌抑制剤などを用いた薬物療法に加え、再発予防を目的とした生活習慣の見直しも重要です。
症状が軽減しても、食道の炎症が完全に回復していない場合には再発を繰り返すことがあるため、継続的かつ専門的な治療が求められます。
薬物療法
 胃酸の分泌を抑えるお薬を中心に、症状や病状に応じて複数の薬剤を使い分けて対応します。例えば、食道の粘膜を保護するお薬や、消化管の動きを促すお薬などを組み合わせることで、より効果的に症状の改善を図ります。多くの場合、服用を始めると比較的短期間で不快な症状は落ち着きますが、炎症が残っている状態で服用を止めてしまうと、再発するケースが少なくありません。そのため、医師の指示に従って服薬を続けることが重要です。
胃酸の分泌を抑えるお薬を中心に、症状や病状に応じて複数の薬剤を使い分けて対応します。例えば、食道の粘膜を保護するお薬や、消化管の動きを促すお薬などを組み合わせることで、より効果的に症状の改善を図ります。多くの場合、服用を始めると比較的短期間で不快な症状は落ち着きますが、炎症が残っている状態で服用を止めてしまうと、再発するケースが少なくありません。そのため、医師の指示に従って服薬を続けることが重要です。
また、炎症を慢性化させないためには、食事内容や生活習慣の見直しも並行して行う必要があります。再発を繰り返すことで、将来的に食道がんのリスクが高まる可能性もあるため、早めに対処しておくことが望ましいでしょう。
治療でよく使用されるお薬には、プロトンポンプ阻害薬(PPI)があり、これは胃酸の分泌を強く抑える作用があります。また、H2ブロッカーという胃酸の分泌を抑える別のタイプのお薬が選ばれることもあります。蠕動運動の機能が低下している場合は、消化管運動改善薬によって内容物の滞留を防ぎ、炎症の悪化を抑えます。必要に応じて、粘膜を保護するお薬や制酸剤を併用することで、症状のコントロールをさらに強化します。
服薬について
多くのお薬は、食前、食後、食間など服用のタイミングが決められています。これは、それぞれのお薬が最も効果を発揮できるように設計されているためで、正しいタイミングでの服薬が治療効果に直結します。消化管はお薬の影響を直接受ける臓器であり、胃酸や消化酵素の分泌タイミングに応じてお薬が吸収・作用するよう作られていることからも、用法を守ることが大切です。
また、症状が治まったように見えても、粘膜の修復には時間がかかるため、一定期間は服薬を継続する必要があります。自己判断で治療を中断してしまうと再発を招きやすく、長期的には食道がんのリスクが高まる可能性もあるため、医師の指示通りに服用を継続してください。
当院では、各患者様の生活スタイルやご希望に寄り添いながら、無理のない服薬スケジュールを考慮した処方を行っています。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
生活習慣の改善
発症や悪化には、食事内容や腹部への圧力など、日常の生活習慣が深く関わっています。
そのため、再発を防ぐためにも、無理なく継続できる範囲から生活習慣を見直していくことが大切です。
食事のポイント
脂質やタンパク質を多く含む食事は、胃酸の分泌を活発にし、消化にも時間がかかるため、逆流リスクが高まります。また、香辛料や甘いものなど刺激の強い食品も、症状を悪化させる一因となるため摂りすぎには注意が必要です。 さらに、飲酒や喫煙も逆流性食道炎の発症・悪化を引き起こしやすいため、節酒や禁煙に取り組むことが望まれます。便秘が続くと腹圧が上昇しやすくなるため、食物繊維や水分をしっかり摂るなど、腸内環境の改善にも努めましょう。
当院では、便秘のある方に対して、逆流性食道炎と合わせた総合的な治療を行っています。
腹圧への対策
胃にかかる圧力が増すことで逆流のリスクが高まります。そのため、腹圧を上昇させる要因への対応が必要です。具体的には、肥満の解消、ベルトや締め付けの強い衣類の見直し、猫背など姿勢の改善、無理な運動や重い荷物の持ち上げに注意することなどが挙げられます。
当院では、各患者様の生活習慣に応じた対策方法をご提案しています。
その他
食後すぐに横になると逆流しやすくなるため、食後は2時間以上空けてから就寝するようにしてください。横になると咳が出る場合には、逆流によりのどが刺激されている可能性があります。そのような場合は、クッションなどを使って上半身を少し高くして寝ることで、咳の軽減に繋がることがあります。







