インフルエンザワクチンについて
 インフルエンザは、例年12月頃から翌年3月頃にかけて流行のピークを迎えます。
インフルエンザは、例年12月頃から翌年3月頃にかけて流行のピークを迎えます。
ワクチンは接種後、効果が現れるまでにおよそ2週間かかり、その効果は約5ヶ月間持続します。
そのため、流行が本格化する前の11月中旬までに接種を済ませておくことが推奨されます。
| 予防接種費用 | ○○円(税込) |
|---|---|
| 八王子市に住民票を置く65歳以上の方 | ○○円(税込) |
インフルエンザは風邪と異なります
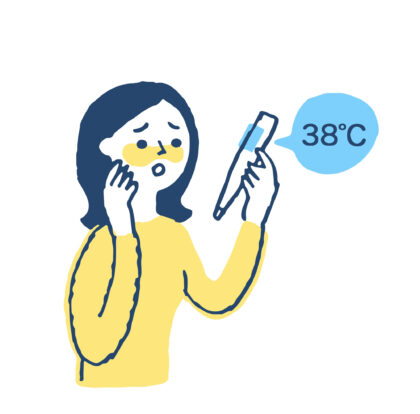 インフルエンザはインフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症で、いわゆる「風邪」とは異なる病気です。
インフルエンザはインフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症で、いわゆる「風邪」とは異なる病気です。
発症すると、咽頭痛・鼻水・咳といった風邪に似た症状に加え、高熱(38℃以上)や強い倦怠感、関節痛、筋肉痛などの全身症状が現れます。
また、吐き気や腹痛など、消化器系の症状を伴うこともあります。
さらに、インフルエンザでは合併症にも気を付けなければいけません。
特に高齢者(65歳以上)、5歳未満の乳幼児、妊婦、糖尿病などの慢性疾患を持つ方は重症化しやすく、インフルエンザ脳炎やウイルス性肺炎など、命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。
こうした重症化リスクを避けるためにも、早めの予防対策が重要です。
インフルエンザの流行について
インフルエンザは、例年12月から翌年3月にかけて流行するとされてきましたが、近年では季節に関係なく散発的に発生する傾向も見られ、通年での注意が必要な感染症となりつつあります。
そのため、日頃から十分な睡眠、栄養バランスの取れた食事、手洗いやうがいの習慣を心がけ、インフルエンザの予防と免疫力の維持に努めることが大切です。
また、冬の本格的な流行期に備え、早めにワクチン接種を希望される方も多くいらっしゃいますが、インフルエンザワクチンの効果はおよそ5ヶ月とされています。
流行のピークを迎える1〜2月にしっかりと効果を発揮させるためには、「10月中旬から11月下旬まで」に接種を受けておくことが推奨されます。
インフルエンザの潜伏期間
インフルエンザは、ウイルス感染から1〜3日程度の潜伏期間を経て発症します。個人の体質や年齢、体調によって差はありますが、平均的には2日ほどで発症するケースが多いです。
なお、ウイルスはわずか1日で急速に増殖するため、感染後すぐに症状が現れることも少なくありません。
また、症状が出ていない潜伏期間中であっても、周囲に感染を広げる可能性があるため、十分な注意が必要です。
インフルエンザの感染経路
インフルエンザは主に「飛沫感染」と「接触感染」の2つの経路で広がります。
感染の仕組みを正しく理解し、日常生活の中で予防策を意識することが大切です。
飛沫感染
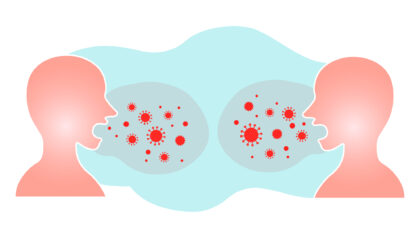 飛沫感染は、感染者のくしゃみや咳によって放出されたウイルスを含む飛沫を、周囲の人が吸い込むことで感染が広がる経路です。
飛沫感染は、感染者のくしゃみや咳によって放出されたウイルスを含む飛沫を、周囲の人が吸い込むことで感染が広がる経路です。
繁華街や学校、職場など人が集まる場所では飛沫感染のリスクが高まるため、マスクの着用や咳エチケットなどの対策を心がけましょう。
接触感染
接触感染は、感染者がくしゃみや咳をする際に手で口元を覆うことで、手に付着したウイルスが原因となります。
ウイルスが付着した手でドアノブやスイッチ、電車の吊り革などに触れると、ウイルスが様々な場所に広がってしまいます。
他の人がその場所に触れた後、自分の鼻や口、目などに触れることで感染が起こります。
インフルエンザの予防法
インフルエンザの感染拡大を防ぐためには、飛沫感染と接触感染の両方にしっかりと対策を講じることが重要です。
日頃から咳エチケットを守り、「自分がうつさない」「他人からうつされない」ことを意識して行動しましょう。
手洗いをしっかり行いましょう
 「帰宅後」や「調理の前後」、「食事前」などには、石鹸を使って丁寧に手を洗うことが感染予防の基本です。
「帰宅後」や「調理の前後」、「食事前」などには、石鹸を使って丁寧に手を洗うことが感染予防の基本です。
特に、電車やバスの吊り革、ドアノブ、手すり、エレベーターのボタン、電気のスイッチなど、不特定多数の人が触れる場所にはウイルスが付着しやすいため注意が必要です。
外出中にこまめな手洗いが難しい場合には、「消毒用ウェットティッシュ」や「アルコール消毒液」などを携帯し、手指の消毒を心がけましょう。
外出時のマスク着用と咳エチケットの徹底
マスクの着用は、自分が感染源となって他人にうつさないための重要な予防手段です。
現在のところ、ウイルスを完全に遮断できるマスクはありませんが、着用することで飛沫の拡散を抑え、一定の感染予防効果が期待できます。
また、のどが乾燥すると粘膜の防御力が低下し、感染しやすくなるため注意が必要です。
マスクには口腔内の保湿効果もあり、インフルエンザ予防に有効です。
咳エチケットを心がけましょう
体調の良し悪しにかかわらず、くしゃみや咳が出る場合は、必ず咳エチケットを守り、マスクを着用するようにしましょう。
インフルエンザに感染していても、症状が軽い、あるいは全く現れない「不顕性感染」もあります。
そのため、本人も周囲も感染に気づかず、知らないうちにウイルスを広げてしまうことがあります。
感染拡大を防ぐためには、それぞれが咳エチケットを守ることが非常に重要です。
小さな配慮でも、社会全体で意識することで、インフルエンザの感染リスクは大きく減らすことができます。
十分な栄養と睡眠を心がけましょう
免疫力が低下すると、インフルエンザにかかりやすくなり、重症化のリスクも高まります。
そのため、日頃から栄養バランスの良い食事を心がけ、質の良い睡眠をしっかりと取ることが大切です。併せて、過度なストレスを避けることも、免疫力を維持するためには重要なポイントです。
免疫力を高める食事
免疫力の維持・向上のためには、腸内環境を整えることが大切です。納豆やヨーグルトなどの発酵食品は、免疫機能のサポートに役立ちます。
湿度を保ち、室内の乾燥を防ぎましょう
空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御力が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。特に乾燥しやすい冬場の室内では、加湿器や濡れタオルを活用して、湿度を50〜60%に保つよう心がけましょう。
加湿器がない場合でも、お湯を沸かす、洗濯物を室内に干すなど、身近な方法で湿度を調整することが可能です。
繁華街など人の多い場所への外出は控えましょう
インフルエンザの流行期には、できるだけ人の多い場所への外出は控えるようにしましょう。特に、持病のある方や高齢の方、妊娠中の方は重症化のリスクが高いため注意が必要です。また、寝不足や体調不良を感じている方も、無理な外出は避けるよう心がけましょう。
インフルエンザの予防には予防接種を
インフルエンザは、1週間ほどで回復することが多い感染症ですが、なかにはインフルエンザ脳炎やウイルス性肺炎など、深刻な合併症を引き起こすケースもあります。
ワクチンを接種することで、発症のリスクを抑えるだけでなく、万が一かかってしまった場合でも重症化を防ぐ効果が期待できます。そのため、流行時期を迎える前に予防接種を受けましょう。







