肛門周囲膿瘍とは
肛門と直腸の境目にある「歯状線」と呼ばれる部分が損傷すると、便に含まれる細菌が侵入し、炎症を引き起こすことがあります。
この炎症が肛門周囲に広がり、膿が溜まった状態が「肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)」です。さらに病状が進行すると、膿が皮膚の下にトンネル状の通路(瘻管)を形成し、「痔ろう(あな痔)」へと移行します。痔ろうは、膿の通り道が複雑に枝分かれすることもあり、強い痛みや高熱を伴うことがあります。 稀に、痔ろうが長期間続くことでがん化することもあるため注意が必要です。排便時に膿が混じる、肛門付近にしこりや違和感がある場合は、早めに医療機関を受診してください。
症状
 肛門周囲膿瘍の症状は、膿が溜まる位置によって異なります。皮膚の近くに膿瘍ができた場合は、肛門周辺に赤みや腫れ、しこりが現れ、強い痛みを伴うのが一般的です。
肛門周囲膿瘍の症状は、膿が溜まる位置によって異なります。皮膚の近くに膿瘍ができた場合は、肛門周辺に赤みや腫れ、しこりが現れ、強い痛みを伴うのが一般的です。
一方、体の深部に膿が溜まるケースでは、外見上の変化が目立たず、しこりに気づかないこともあります。その場合は、倦怠感や微熱、腰周りの鈍い痛みといった全身症状が現れることがあります。 病状が進行して痔ろうになると、膿が排出されるためのトンネル状の通路(瘻管)ができ、膿が皮膚から漏れ出して下着が汚れたり、排便時に膿が混ざったりします。さらに感染が広がると、高熱や激しい痛みに見舞われることもあります。
原因
肛門と直腸の境目には「歯状線」という部分があり、その周辺には「肛門小窩」と呼ばれる小さな窪みがあります。この肛門小窩が損傷を受けると、細菌が侵入して炎症を起こし、やがて膿が肛門の周囲に溜まる「肛門周囲膿瘍」が発生します。
損傷のきっかけには様々で、例えば便に混じった魚の骨などの異物による傷や、下痢・軟便による刺激が挙げられます。さらに、免疫力の低下時や、辛い食事・アルコールの過剰摂取も発症リスクを高めると考えられています。
また、特定の病気が背景にある場合もあり、膿皮症や潰瘍性大腸炎、肛門部のがんなどが原因になることもあります。加えて、温水洗浄便座の使い方にも注意が必要です。過剰な洗浄によって、肛門周りの常在菌まで洗い流してしまうと、かえって感染を起こしやすくなることがあります。
治療
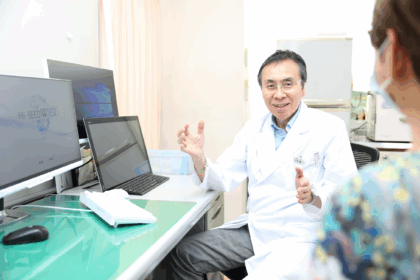 痔ろうや肛門周囲膿瘍まで症状が進行している場合、膿溜まりに抗菌薬が十分に届かないため、内服薬だけでは効果が得られにくいことがあります。そのため、治療の基本は切開によって膿を排出する「切開排膿」が中心となります。
痔ろうや肛門周囲膿瘍まで症状が進行している場合、膿溜まりに抗菌薬が十分に届かないため、内服薬だけでは効果が得られにくいことがあります。そのため、治療の基本は切開によって膿を排出する「切開排膿」が中心となります。
切開にあたっては、視診や触診によって膿が溜まっている部位を確認します。膿瘍が深い位置にある場合は、超音波を使用して正確な位置を把握しながら処置を行います。麻酔の使用については膿の大きさに応じて判断され、大きな膿瘍には局所麻酔を用いますが、小規模な場合には麻酔を使わずに処置することもあります。







