ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)とは
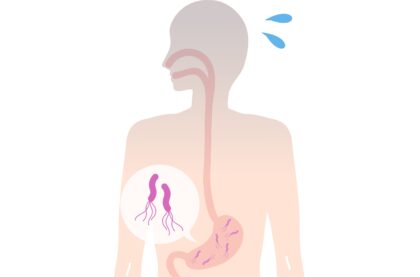 ピロリ菌は、強い酸性環境である胃の中に生息できる珍しい細菌です。
ピロリ菌は、強い酸性環境である胃の中に生息できる珍しい細菌です。
通常の細菌が生きられない胃粘膜において、ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を利用して周囲の胃酸を中和し、活動できる環境を自ら作り出しています。 感染は、汚染された水を介して起こると言われており、上下水道が整備された先進国では感染率が減少しています。しかし、日本ではいまだに高い感染率が報告されており、特に家族間での口移しなどによる経口感染が指摘されています。家族に胃・十二指腸潰瘍や胃がんの既往がある場合は、ピロリ菌に感染している疑いが強いとされています。
ピロリ菌に感染すると、胃や十二指腸に慢性的な炎症を引き起こし、潰瘍や胃がんなどの疾患のリスクが高まります。ただし、抗生物質を使った除菌治療によって、ピロリ菌は体内から除去することが可能です。除菌により、炎症や潰瘍の再発を防ぐことができるほか、他の人への感染リスクを抑える効果も期待できます。
ピロリ菌の感染検査
ピロリ菌の検査は、胃カメラを用いて胃の組織を採取して行う方法と、胃カメラを使用しない方法の2種類があります。
胃カメラを用いた方法
除菌治療を保険適用で行うには、胃カメラ検査が必須です。
胃内の組織を採取し、以下のいずれかの検査を行います。
- 迅速ウレアーゼ試験:
ピロリ菌が産生するウレアーゼという酵素の働きを利用して、感染の有無を素早く判定します。
採取した組織に反応させることで、短時間で結果が得られます。 - 鏡検法:
採取した組織を染色して顕微鏡で観察し、ピロリ菌の存在を直接確認する方法です。 - 培養法:
組織を培養し、ピロリ菌が実際に増殖するかどうかを調べる検査です。
胃カメラ検査を使用しない方法
- 尿素呼気試験:
検査薬を服用し、服用前後の呼気を採取して調べる方法です。
精度が高く、除菌治療後の判定にもよく使われています。 - 抗体測定:
血液または尿を採取し、ピロリ菌への抗体が存在するか調べる検査です。 - 便中抗原測定:
便に含まれるピロリ菌の抗原を調べる方法で、現在の感染状態を評価するのに用いられます。
胃がんリスク検診
 近年では、血液を用いた胃がんリスク検診が広く実施されるようになっています。
近年では、血液を用いた胃がんリスク検診が広く実施されるようになっています。
この検査は、採血によってピロリ菌抗体の有無を調べるとともに、胃粘膜の状態を反映するペプシノーゲンの値を測定することで、胃の炎症や萎縮の進行度を評価します。これらの検査結果を組み合わせて、将来的な胃がんの発症リスクを分類・判定するスクリーニング検査です。
ただし、この血液検査だけでは正確ながんの有無までは判断できません。胃がんの早期発見や確定診断には、胃カメラ検査が不可欠です。血液検査でリスクが高いとされた場合には、速やかに胃カメラ検査を受けることが重要です。
ピロリ菌感染によりリスクが高まる疾患
ピロリ菌はアンモニアなどの有害物質を産生し、長期にわたり胃や十二指腸の粘膜に慢性的な炎症を引き起こすことで、様々な疾患の発症を招きます。
炎症が継続することで粘膜の損傷が蓄積し、組織の修復が間に合わなくなると、やがて深い傷となって潰瘍を形成します。また、炎症の進行によって胃粘膜が萎縮していくと、胃がんのリスクが高まることも知られています。
ピロリ菌を除菌することで炎症や潰瘍の再発リスクは大幅に抑えられ、胃がんのリスクも大きく低下します。なお、完全にリスクを抑えられるわけではないため、除菌後も定期的に胃カメラ検査などを受け、早期発見に努めることが重要です。
以下は、ピロリ菌との関連が指摘されている疾患です
- 機能性ディスペプシア
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
- 胃ポリープ
- 胃MALTリンパ腫
- 胃がん
- 特発性血小板減少性紫斑病
- 慢性蕁麻疹 など
ピロリ菌と胃がんの関係
近年の国内外の研究により、ピロリ菌が胃がんの発症に大きく関与していることが明らかになっています。ピロリ菌に感染すると、慢性的な胃の炎症が続き、その結果として胃粘膜が萎縮し、胃がんのリスクが高まることが知られています。
ピロリ菌の除菌治療は、胃や十二指腸の様々な疾患の改善に効果があるだけでなく、炎症の進行を食い止めて萎縮を防ぐことで、胃がんの予防にも一定の効果が見込まれます。なお、除菌を行っても胃がんのリスクが完全になくなるわけではありません。そのため、除菌後も定期的に胃カメラ検査を受けることが重要です。
早期の段階で微細ながんを発見できれば、身体への負担を最小限に抑えた治療が可能となり、完治も十分に期待できます。
除菌治療
ピロリ菌の除菌は、2種類の抗生物質と胃酸の分泌を抑えるお薬を1週間服用することで行います。初回の除菌では、約9割の方が成功するとされています。除菌が完了したかどうかを正しく判断するためには、お薬の服用終了後すぐには検査を行わず、少なくとも1ヶ月以上の期間を空けてから判定検査を行う必要があります。
万が一、1回目の治療で除菌が不十分だった場合には、使用する抗生物質を一部変更し、2回目の治療を実施します。1回目と2回目の治療を合わせた成功率はおよそ99%にのぼると報告されています。 胃カメラ検査によりピロリ菌感染が確認された場合、初回と2回目までの除菌治療には健康保険が適用されます。
それ以降の治療を希望される場合は、自費診療となりますが、継続的な治療が可能です。
治療の副作用について
除菌治療では、一時的な副作用が現れることがあります。
代表的なものとしては、軟便や下痢、吐き気、味覚の変化などが挙げられます。これらの症状は通常、1週間の服用が終了してから自然と落ち着いていきますが、症状が気になる場合は無理をせず、早めに医療機関へご相談ください。
また、治療後に胸やけやのどの違和感など、逆流性食道炎に似た症状が一時的に出ることもあります。これは除菌によって胃の環境が変化する影響で起こるもので、多くは時間の経過とともに改善します。しかし、症状が強い場合や長引くようなときには、放置せずに医師の診察を受けてください。







