食欲不振について
 食欲不振とは、文字通り「食欲が湧かない」「食べたくない」といった状態です。消化器と脳は密接に連携しており、通常は食事によって腸が刺激されると、脳が空腹を感じて「お腹がすいた」とサインを出します。この連携に何らかの不調が起こると、食欲が湧かなくなってしまうことがあります。
食欲不振とは、文字通り「食欲が湧かない」「食べたくない」といった状態です。消化器と脳は密接に連携しており、通常は食事によって腸が刺激されると、脳が空腹を感じて「お腹がすいた」とサインを出します。この連携に何らかの不調が起こると、食欲が湧かなくなってしまうことがあります。
食欲が長く低下したままだと、全身の栄養状態が悪化し、免疫力が落ちたり、体調を崩しやすくなったりします。原因は、ストレスや疲労など一過性のものから、消化器系を含む病気まで様々です。食欲不振が続く場合には、軽く考えず、早めに当院までご相談ください。
食欲不振は様々な原因が考えられます
腹痛は様々な疾患に伴って現れる一般的な症状ですが、夜間に腹痛が生じる背景には、大腸に関わる疾患が潜んでいることがあります。
以下は、夜間の腹痛の原因として考えられる主な疾患です。
感染症やその他の疾患
食欲不振の背景には、実に多くの要因が考えられます。
代表的なものとしては、機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群、逆流性食道炎、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、食道がんなどの消化器系の病気や、脳腫瘍などの脳の疾患、心不全などの循環器疾患、腎臓や肝臓の障害、頭痛、電解質バランスの異常などが挙げられます。また、風邪やインフルエンザ、気管支炎、肺炎といった感染症による体調不良、虫歯・歯周病・口内炎といった口腔内のトラブルも、食欲を低下させる一因です。
甲状腺機能低下症(橋本病)
慢性甲状腺炎や放射線の影響などにより甲状腺機能が低下すると、ホルモン分泌が不足し、体全体の活力が落ち、疲れやすさや倦怠感、食欲不振といった症状が現れます。
ストレス
精神的ストレス(不安、悲しみ、怒りなど)や、過労による肉体的ストレスは、自律神経の働きを乱し、特に副交感神経の機能を低下させることで、食欲不振を招くことがあります。
生活習慣の乱れ
運動不足や睡眠不足、不規則な食事時間といった生活習慣の乱れも、自律神経のバランスを乱し、食欲の低下に繋がります。
さらに、過剰なアルコール摂取は肝臓に負担をかけ、食欲を落とす原因となることがあります。
食欲不振の原因となる消化器疾患
胃がん
胃がんが進行すると胃の働きが低下し、食欲も次第に低下していきます。初期の段階では目立った症状が現れにくいため、気づかずに進行しているケースも少なくありません。
機能性ディスペプシア
明確な病変が見られないにもかかわらず、胃の不快感やもたれ、痛みなどの症状が出る疾患です。食欲不振を伴うこともあります。
慢性胃炎(萎縮性胃炎)
主な原因はピロリ菌の感染です。感染により胃の粘膜がダメージを受けると、胃の機能が低下し、食欲が落ちることがあります。
胃・十二指腸潰瘍
胃や十二指腸の粘膜が深く傷つくことで、腹痛や吐き気が現れます。幽門(胃の出口)付近に潰瘍ができると、食べた物が胃に留まりやすくなり、膨満感や不快感から食欲不振が引き起こされます。
食道がん
食道がんが悪化した場合、飲食物の通過が妨げられ、食べにくさや飲み込みにくさが生じます。それに伴って食欲が低下することがあります。初期段階ではほとんど症状が見られません。
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流することで食道に炎症を起こす疾患です。主な症状は胸やけや呑酸(酸っぱい液がこみ上げる感じ)ですが、人によっては食欲が落ちることもあります。
食欲はあるのに体重が減る…気を付けたい体重減少について
 明らかな原因がないまま体重が減少している場合、何らかの疾患が関与している可能性があります。食欲が低下して食事量が減ることで体重が落ちるケースもあれば、食欲があり十分に食べているにもかかわらず、体重が減ってしまうこともあります。
明らかな原因がないまま体重が減少している場合、何らかの疾患が関与している可能性があります。食欲が低下して食事量が減ることで体重が落ちるケースもあれば、食欲があり十分に食べているにもかかわらず、体重が減ってしまうこともあります。
特に、短期間で急激に体重が減少している場合には、早急な対応が必要な病気が潜んでいる可能性もありますので、早めに医療機関を受診することが大切です。 また、過度なダイエットや激しい運動によって体重が落ちた場合には、栄養バランスの乱れに繋がりやすく、体調を崩したり、身体機能に悪影響を及ぼす恐れがあります。体重の変化には日頃から注意し、無理のない健康管理を心がけましょう。
日常生活が起因となる体重減少
ダイエット
過度な食事制限や偏った栄養摂取は、身体に必要な栄養素が不足しやすく、健康を損なう要因となります。こうした無理なダイエットを続けると、神経性食欲不振症(拒食症)に移行することもあるため注意が必要です。体調を維持するには、栄養バランスの取れた食事が欠かせません。
精神的ストレス
強いストレスや不安が続くと、自律神経の働きが乱れ、胃腸の動きが低下して食欲が落ちたり、消化がうまくいかなくなったりします。その結果、体重が落ちてしまうことがあります。また、ストレスは機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群、逆流性食道炎、便秘や下痢といった消化器の不調を引き起こし、それも体重減少に拍車をかける原因となります。
過剰なエネルギー消費
激しい運動や長時間労働により、摂取したエネルギーが消耗されすぎると、十分に食べているつもりでも体重が減ってしまいます。若年層であっても、栄養不足が続くことで骨密度が低下し、骨折のリスクが高まります。女性では、ホルモンバランスが乱れて月経が止まることもあります。
進行がん
がんが進行すると、明らかな症状が出る前に体重減少が現れることがあります。他に目立った体調の変化が見られないことも少なくありません。
体重減少の原因となる疾患
神経性食欲不振症(拒食症)
標準体重を大きく下回っていても、体型への強いこだわりや肥満への恐怖から、さらに減量を続けてしまう摂食障害の1つです。過度な食事制限や、嘔吐、下剤の多用などが見られます。元気に見えることもありますが、深刻な疾患や命に関わる状態が潜んでいる可能性もあるため、早期の受診が必要です。
糖尿病
「太る病気」と思われがちですが、進行すると体重減少を伴うこともあります。インスリンの作用が低下すると、糖をエネルギーとして利用できなくなり、代わりに脂肪や筋肉が分解されて体重が落ちていきます。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
甲状腺は、成長や代謝を調整するホルモンを分泌する重要な臓器です。バセドウ病では、基礎代謝が異常に高まり、エネルギーが消費されすぎて体重が減少します。 さらに、体は常に運動しているかのような興奮状態となり、特に心臓には大きな負担がかかります。これに伴い、汗が多くなる、寝つきが悪くなる、動悸がするなど、様々な不調が現れます。
これらの症状は、自律神経の乱れや更年期による体調変化と間違われることもあります。 バセドウ病は一般的な健康診断では見逃される場合もあるため、正確な診断には血液検査が必要です。早期に発見して治療を開始すれば、症状の改善が十分に見込めます。
慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍
これらの疾患では、胃や腸の粘膜が炎症や潰瘍によって機能低下を起こし、食欲不振や消化吸収力の低下に繋がります。ピロリ菌の感染が主な原因とされており、除菌によって改善が見込まれます。また、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)も発症の要因となるため、お薬の見直しが必要なケースもあります。
潰瘍性大腸炎・クローン病
慢性的な腸の炎症が続くこれらの病気では、下痢や血便とともに体重減少が起こることが多くあります。潰瘍性大腸炎は大腸に、クローン病は消化管全体に炎症が広がる可能性があります。症状のある時期と落ち着く時期(寛解期)が交互に訪れ、継続的な治療が必要な難病です。
吸収不良症候群
消化や吸収がうまくいかず、体に必要な栄養素や水分を取り込めなくなる病態です。その結果、体重が減るほか、下痢、貧血、むくみ、脂肪便といった様々な症状が現れます。原因が多岐にわたるため、正確な診断が重要です。
消化器がん(胃がん・大腸がん・膵臓がんなど)
がんの進行により、正常な消化機能や栄養吸収が妨げられ、がん細胞がエネルギーを消費することもあって、体重が徐々に減少します。食欲の低下や全身状態の悪化も影響し、体重減少が現れる場合があります。思い当たる原因がなく体重が落ちる場合は、早めに専門医の診察を受けることが勧められます。
うつ病
うつ病では、興味や関心の喪失、無気力とともに食欲も失われやすくなり、体重が減少することがあります。放置すると症状が悪化するため、早期の診断と適切な治療が大切です。
食欲不振・体重減少の検査
 まずは、食欲不振がいつから始まったか、どのくらいの頻度で起きているか、体重の変化や過去の病歴、付随症状の有無などについて、丁寧に問診を行います。また、生活習慣の乱れや精神的ストレスといった心理的な要因についても詳しく確認していきます。
まずは、食欲不振がいつから始まったか、どのくらいの頻度で起きているか、体重の変化や過去の病歴、付随症状の有無などについて、丁寧に問診を行います。また、生活習慣の乱れや精神的ストレスといった心理的な要因についても詳しく確認していきます。
問診の結果、特定の疾患が疑われる場合には、必要に応じて血液検査、腹部超音波検査、内視鏡検査、CT検査などの精密検査を行います。食道・胃・十二指腸に異常が考えられる場合は胃カメラ検査が、大腸に関する異常が疑われる場合は大腸カメラ検査が有効です。
当院では、熟練の内視鏡専門医が在籍しており、できる限り負担を抑えた検査を提供しています。安心してご相談ください。
食欲不振・体重減少の治療
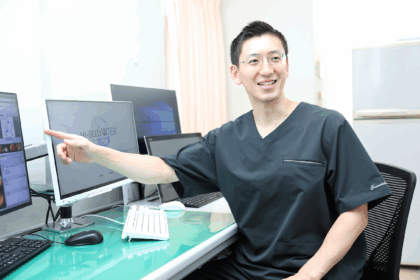 食欲不振や体重減少には、精神的ストレスや生活習慣の乱れといった一過性の要因から、食道がん・胃がん・大腸がん・膵臓がんなどの重大な病気、脳や心臓の疾患まで、様々な要因が関係しています。
食欲不振や体重減少には、精神的ストレスや生活習慣の乱れといった一過性の要因から、食道がん・胃がん・大腸がん・膵臓がんなどの重大な病気、脳や心臓の疾患まで、様々な要因が関係しています。
当院では、症状の原因を丁寧に見極めたうえで、適切な検査と治療を行っています。診療の結果、他の診療科での治療が必要と判断された場合には、専門性の高い医療機関や専門医へのご紹介も行っています。また、ストレスや不規則な生活リズムが原因となっている場合には、生活習慣の見直しやストレス対策、適度な運動などについての指導も行っております。お気軽にご相談ください。







